研究室 修士学生 が筆頭で執筆した論文が 世界的トップジャーナル Applied Thermal Engineering (IF=5.295) にて採択・掲載
熱工学分野の世界的なトップジャーナルの1つ,Applied Thermal Engineering (IF=5.295) に,2021年9月付で掲載されました.
筆頭著者は,修士2年の渡邊廉君で,修士1年の時に執筆して,4名の査読者と3 度(3度目は2名)の査読者とのやりとりを経て採択され,掲載にいたりました.
元々はNEDOプロジェクトで,東京農工大学の秋澤淳教授(研究筆頭代表)からLNG(液化天然ガス)の冷熱回収用の熱交換器研究設計依頼を受け,NEDOから本学へ委託され研究開発したものです(受託先研究代表および本論文の責任著者:榎木).
論文は以下のリンクで取得できます.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2021.117284
この論文発表での特徴は,以下の2点に集約されます.
● 熱伝達の悪い空気を通常の内径 12 mm から 18 mm の伝熱管に流しても,150 mm の伝熱管長では熱回収はほとんど不可能です.
だから入口温度 200 ℃ で伝熱管外部の周囲温度を2℃で均一に冷やしても,出口温度は 130 ℃ 程度で出てきます.
しかし,この中にアルミ繊維体を 20 % の空間割合で(すかすかの状態で),25 mm と親指の第一関節程度の短い長さ管内に充填させると,出口温度は冷却温度の 2 ℃ の冷風が得られます.
つまり,ほぼ 100 % の空気の熱回収をたった 25 mm で回収できたことになります.
専門的に言えば,水の強制対流熱伝達よりも,この伝熱管を用いた空気の強制対流熱伝達の方が高く,相変化熱伝達と同じオーダーの熱伝達率を達成したことが,本件研究の一番の特徴です.
● 摩擦圧力損失を正確に見積もることは機械機器の設計に非常に重要です.
このため,伝熱管内径はもちろん,アルミ繊維体の空間割合を変化させたり,繊維の細さや繊維の充填長さを変化させて実験を行いデータ整理しました.
その結果,実験結果を ± 12 %で再現する整理式の構築ができました.
他研究者の実験結果とも比較して,一般化された整理式としています.
この研究成果は実用面において,現在工場等で廃棄されている 200 ℃ 程度の排熱の回収や,純アルミのみで作成されているので低温脆化が生じにくい性質があることからマイナス 200 ℃ 程度で輸送されるLNGの冷熱回収に使用できます.つまり,軽量のアルミで内径 20 mm 以下で,多孔質体充填長さ 25 mm(アルミの空間割合 20 %)の幼児でも片手で持つことができる軽さの伝熱管でありながら,高温でも低温でも温度差 200 ℃ を取得可能な,軽さと使用材料の少なさを両立させた,大量の熱を授受できる伝熱管です.
言い換えれば,世界に類をみない省資源で省エネルギーに貢献する伝熱管の1つと言えます.
例えば飛行機の窓の厚さはちょうど25 mm程度と今回の伝熱管の充填長さと同程度です.
上空 10,000 mの上空を飛行してれば外気はおよそマイナス 40 ℃,室内は 20 ℃ と考えるとその温度差は 60 ℃で,60 ℃の温度変化で人間にとっては生きるか死ぬかの死活問題になりかねない温度です.
飛行機の窓ガラスと同じ2.5 cmで,200 ℃ の温度差が達成できる凄さが理解できるかと思います.
《参考:日本国内で1年間で捨てられる200 ℃ 以下の排熱エネルギーの量は,84.6 PJ / 1 Year です.これは,投入エネルギーの約 7 %に相当し,日本の総発電量の約 2.4 %ものエネルギーを大気中に捨てています.
また,エネルギー [J] ですので,地震のエネルギーとも比較できます.84.6 PJは阪神淡路大震災の約 42 倍にもなり,広範囲で地球の一部を動かすことをできる,恐ろしいほど大量のエネルギーが廃棄されています.
(PJのPはペタとよび,Tテラの1,000倍に相当し,10の15乗を意味します.)
また,LNGは使う時は気体です.そこで液体で輸入されるLNGは海の温度で温めて気化していますが,そこで捨てられる冷熱は,LNGが有する発熱量の 1 – 2 %程度にもなります≫
つまり,カーボンニュートラルやサステイナブルな社会の実現への大きな第一歩として貴重な意味を持つ論文となりました.
実験装置は本研究室に設置していて,どなたでも体験することが可能です.
マジックショーみたいで楽しく熱工学を体験できるので,体験希望は ”お問い合わせ” からお願いします.
謝辞
本研究を遂行するにあたり,三菱マテリアル中央研究所の多大なるお力添えがあったことをここに記してお礼申し上げます.
また,本研究は,新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から助成を受けたものである.ここに記し,謝意を表します.[grant number 17100192-0]
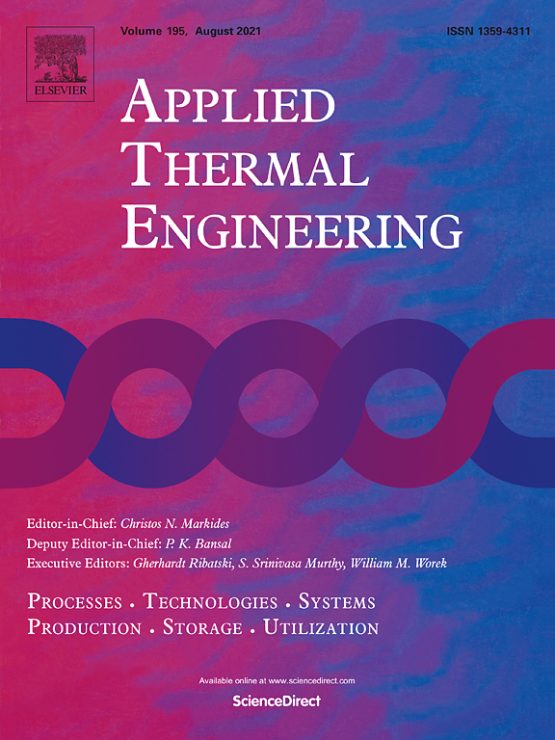
カテゴリー
アーカイブ
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年11月
- 2024年9月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年3月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年4月
- 2021年1月
- 2020年10月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月


